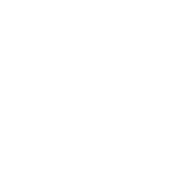栄光ヒュッテ有志キャンプ・熊さん
「この風を感じて欲しいんすよ」
2025年9月初旬。丹沢の栄光ヒュッテにて、2泊3日の有志キャンプが行われた。
栄光学園の卒業生らが作り上げたこの山小屋は、近年、有志企画のキャンプで使われることが多い。
山小屋宿泊、進んでその引率にたずさわる教員がいる。通称“熊(くま)さん”。
山小屋運営のいろは、ソロキャンプの諸知識はもちろんのこと、山小屋における諸企画、「青春クリエイト」にも意欲的だ。
どうして栄光ヒュッテ宿泊のような、タフな活動にいそしんでいるのだろうか。
「携帯やゲームやテレビや、そうした便利なものが何もないところで、何か見つけて欲しいんすよね」。熊さんはそう語る。
山小屋に便利なものは何一つない。夏は、ヒルをはじめとした恐ろしい虫がいるし、トイレも「おがくずトイレ」(水洗ではないトイレ)だ。キャンプに参加する生徒でさえ、こうした不便さに抵抗を示す。それでも来てみる、また来てしまう。不便さを弾き飛ばして余りある喜びが、ここにはある。
昼食を終えるや否や、山小屋は空っぽに。ヒュッテに面した小川で泳ぐ、魚をつる、潜る、石で堤防をつくる、上流へ向かう。
水着や水中用サンダルを持参し忘れた者も、我慢できなくなってくる。水に飛び込む。裸足で小石を踏みつけては上流へ、みなを追う。
「そんな痛いことしてまで、おバカだな」などと感心していた私も、傍観者ではいられないようだ。
水着を忘れた生徒が、服のまま(ジーパンで!)滝修行をはじめたのがきっかけだ。
そこにいた者みな、全身で水につからないことに、罪の意識のようなものを抱きはじめる。
気づけば皆、どっぷりと川につかっていた。全身で自然とたわむれる友達を前にして、一人一人が自分を解放するかのように、目の前の瞬間に没頭し、熱中していた。
魚をとったら、さばいて、火で焼いて、その場で食べる。さばき方を知っている先輩が、うろこやら内臓やらの取り方を後輩に教えている。
教室では明かされない一人一人の一面が、そこら中に散らばっている。夜はたきび台をつくって、火をおこし、はんごう(お米をたくこと)を楽しむ。
熊さんから学んだコツを生かしながら、生徒たちは火を強めたり、弱めたり。薪(まき)の組み方を工夫して、自在に火力をあやつる生徒もいる。
気づけば「火の近くには人が寄ってくる」。特別な何かはなくとも、熊さんの言った通りに。
本物の火は見ているだけで楽しく、心も体も、奥から温まるよう。「何もない」を満喫している若者であふれていた。
山の夜は、暗い。火や懐中電灯のないところでは、何も見えない。本当の夜の暗闇。
それは当たり前だけれど、都会生活では忘れがちなこと。小屋から少し離れたトイレに行くことすら、「怖いから、連れションします」。
電灯の電池が切れてしまった生徒は「(日常生活では)夜でも明るいということのすごさを実感した」ようだ。
自然の根源的な現象を知り、それに感謝できる。日常の当たり前に驚くことができる。
こうした感性を自分の内に思い出すことは、すべての学びの根っこではないか。
当たり前に存在する電灯に、ありがたみを覚えるからこそ、「光を人間が発明する」すごさを感じ取り、さらに興味をもち、学ぶ意欲が湧くのだろうし、
「夜が怖い」という感覚を思い出したからこそ、昔の人々の生活が想像でき、そうした感覚から生まれる風習や伝統、信仰のようなものまで考えるきっかけが生まれるのだろう。
「夜が夜であること」に驚くことのできる贅沢が、ここにはある。
今回の熊さん「青春クリエイト」は、うどんづくりだった。昼に食べるうどんをつくる。各班ごと、一からはじめる。
「どうやったらおいしくなるか、研究したんすよ」と準備万端の熊さん。ひたすらに生地を踏むこと、これである。こねおわって生地を寝かしつけてから、ふみふみ大会。
全身で一から作ったものを食べる経験、それを班で分かち合う経験をしたと同時に、ふつうの「麺の切れない長いうどん」が、いかにむずかしいことなのか、
切れ切れのうどんを頬張りつつ悟ったのである。
山小屋では、チームでまとまり、機敏に動くことも求められる。一人が自分勝手をすると、わかりやすく目立つ環境。何もかもそろっている訳ではない。
運営のノウハウも乏しい。そんな環境において、集団がまとまりを欠けば、仕事は全くはかどらず、楽しい時間ばかり削られていく。
掃除に布団干し、食事作り、そして片付け。そうした何気ない一つ一つの活動においても、生徒に気づいてほしいことはたくさんあるようだ。
うどんを食べ終えた生徒たちは、昆虫を探しに山へ、あるいは川遊びに、三々五々散った。
小屋の前のテエブルには熊さん一人。一通り仕事を終えた熊さんが、珈琲で一息いれている。
少し暑くなってきたが、川のせせらぎが涼しい。ふっと風が吹くと、そよぐ樹々の音も心地よき昼下がり。
「この風を感じて欲しんすよ」。彼らは、きっと何かを感じて帰ってくれたに違いない。そう信じている。